
きくらげって中華料理で使うイメージが強い食材だよね。
でも、鉄分やカルシウムを豊富に含んでいて女性にはオススメの食材の一つなんだって。
私も早速試してみたからレシピや感想を紹介するよ。
きくらげの栄養(概要)
- 食物繊維は、食品中第2位
- カルシウムは、牛乳の2倍
- 鉄分は、レバーの約3.5倍
- ビタミンDは、食品中第1位
食物繊維は、胃の中で水分を吸収して膨らむので、沢山食べなくても満腹感を得られ、ダイエット中に有効です。
また、ビタミンDとカルシウムの十分な摂取が丈夫な骨を造ると注目されはじめています。女性の美容食としても食べられています。
この他にも多くの栄養素を含んでおり、妊活している方に注目の葉酸も含まれています。
ダイエット中の方だけではなく、しっかりと栄養は摂りたいけれど太り過ぎないように注意が必要なプレママさんなどにも適した食材の一つです。
今回試した乾燥キクラゲはこちら

今回試したきくらげ(木耳)はこちらの商品です。地の塩社から販売されているもので、熊本県産です。
湿度や温度などの条件がしっかりと管理された自社工場で生産されているらしいです(メーカー情報)。
熊本で有名なキャラクターの「くまモン」のパッケージで視覚的にも分かりやすいですね。
写真の商品は内容量が45gのものですが、もっと多いものもあるようです。
水で戻すと7~8倍に膨らむ
乾燥きくらげなので、水又はお湯で戻してから使います。
ぬるま湯で20分程度で戻せますが、一晩かけてゆっくりと戻した方が味が良くなると言われているようです。
私は、水でゆっくり戻す方を選択しました。
なお、写真の分量は約5gです。

写真は水を入れたばかりの状態です。水に入れたとたんにどんどん水を吸っていく感じがします。
一晩この状態で置いておくと、次の写真のようになります。

知ってはいましたが、かなり大きくなります。さすがに測るまでしてませんが、7~8倍程度に膨らむみたいです。
使うときは、これを軽く水洗いしてから使います。

一袋45gですが、一度に全てを水に戻してしまうとかなりのボリュームになってしまいます。何度かに分けて使う場合には、残った分はしっかりと封をして冷蔵庫に入れておいた方が良いです(特に夏場)。
きくらげの味がわかるようにおつまみにしてみました
八宝菜などの中華料理に入っているイメージの強いきくらげですが、その素材の味を楽しみたいと考えて、酢をベースにしたドレッシングを和えたおつまみ風にしてみました。
水で戻したきくらげと小ネギを食べ易い大きさに切って、次のドレッシングで和えただけで完成しますから非常に簡単です。
- 醤油 小さじ 2
- 食酢 小さじ 2
- ごま油 小さじ 1
- 砂糖 小さじ 1/2
- レモン汁 小さじ 1/2
- ラー油 少々
- 塩 少々
おつまみきくらげ 完成品はこちら

この量で、乾燥きくらげ約5g分です。
おつまみなので、この分量で4人分くらいかなと思います。
ちなみに、上に乗せた小ねぎは我が家の家庭菜園で取れたものです。このようにちょっとした料理に自分で育てた野菜を加えるとより一層楽しめますよね。
実際に体験(試食)してみた感想
一言で言うと、きくらげはクセの無い味でさっぱりと食べることが出来ました。
これまで、あまり良いきくらげに出会っていなかったのか、きくらげが薬臭いようなイメージを持ってしまっていました。
この地の塩社のきくらげにはそのような薬臭さをを感じる事がなかったので、色々な料理に混ぜる事が出来そうな感じがしました。
正直に言って、私自身これまであまり「きくらげ」が好きではなかったのですが、美味しいものなんだなと感じたのにはビックリです。
なお、子供達は普段はあまりきくらげを食べていないので他のものと比較はできないようでしたが、味は美味しいと言っていましたよ。
更に私自身で、きくらげを食べたときに満腹感が出やすい事を体感出来ました。
上手に使えば、無理せずにダイエットなんてこともできそうですよ。

子供達にはドレッシングの味が薄いと言われたよ。
私はちょうど良いと感じたので、お好みで調整してね。
その他のきくらげに合う料理
この他にもきくらげに合う料理はたくさんあります。
一例ですが紹介しておきます。
- 酢豚
- 麻婆豆腐
- 中華風スープ
- チャーハン
- カレー
- ハンバーグ など
私は、佃煮にしてみましたよ(下の写真)。

こちらも作り方は簡単で、水で戻した「きくらげ」を細かく切って、下の調味料と一緒に鍋で煮るだけです。
- 料理酒 小さじ 3
- みりん 小さじ 3
- 醤油 小さじ 6
- 砂糖 小さじ 2
- 和風だし 小さじ 1/2
- しょうが 適量
- ごま油 お好みで

私は、中華風の佃煮をイメージしてごま油を入れてみたよ。
和風が良ければ、ごま油は入れないで作ってみてね。
今回の食育ポイント
今回は、あえて我が家ではあまり食卓に上がる事がなかった「きくらげ」を体験してみました。
予想通り、小学校6年生の長女も「きくらげ」が何なのか知りませんでした。
新しい事に触れ合ったり、発見したりする事は食育の効率を上げてくれますから、普段と違う食材を使うのは非常に良い事ですよ。
最後に、今回の食育ポイントをまとめてみました。
- きくらげがキノコの一種だということがわかった
- 水につけておくと凄く大きくなることにビックリした
- きくらげ=木耳 ということがわかった
- きくらげを食べると満腹感が出るのを体感できた

同じ食材でも産地によって味が違ったりするから、比較してみるのも食育としてはオススメの方法だよ。
もしかしたら、これまで嫌いだった食材も食べられるようになるかもね!
▼▼▼ きくらげはこちら ▼▼▼
▼ 食育と学力についての記事も見てね ▼



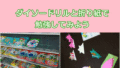

コメント